
Last Updated on 2018-02-21 by ラヴリー
2017年ノーベル文学賞に選ばれた日本生まれの英国人作家カズオ・イシグロ。彼の作品のあらすじや解説、おすすめの本を紹介します。まだ読んだことがなくて、どれから読もうかと迷っている人の参考になればうれしいです。
カズオ・イシグロは寡作の作家ですが、彼の作品を読んでみるとその理由がわかります。似たような作品を次から次に書くような作家ではなく、1冊1冊に長い時間と思索を重ねて試行錯誤の結果、美しい芸術作品に仕上げる小説家なのです。
彼の作品はすべて全く違うプロット、場所、登場人物で、作風も多岐にわたり、読むたびに彼の新しい境地を経験することになるでしょう。
とはいえ、カズオ・イシグロ特有の静かにストーリーが流れるペースやどの作品にも共通するテーマといったものは、あります。登場人物の現在と過去の思い出、記憶が織りなす世界に読む人を引き込まされずにいられないストーリー展開がそうです。
どれから読んだらいいのか、悩んでいる人のために簡単に作品を紹介します。下記はイギリスでオリジナル版が出た年の順に並んでいます。
Contents
遠い山なみの光 (小野寺健訳) A Pale View of Hills (1982)
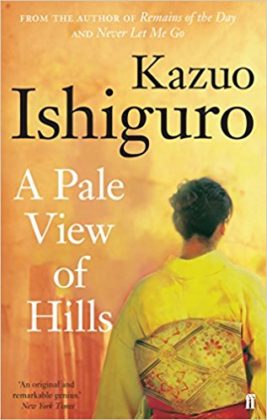
カズオ・イシグロのデビュー作は長崎を舞台としています。
イギリス人と再婚してイギリスに住む、長崎出身の日本人女性、悦子の話。前夫との娘が自殺し、悲しみに暮れる中、悦子は戦後の長崎で過ごした過去を振り返ります。その頃の長崎は戦争、とりわけ被爆の被害があちこちに残っており、生き延びた人たちも混乱の毎日を生きるのに必死でした。そんな中、知り合った女性や前夫、義父などについての思い出が悦子の遠い記憶をたどる形でストーリーを織りなします。
悦子が若かった頃に抱いた希望、あきらめたこと、犠牲にしたもの、新しい人生への期待が入り混じった、ほろ苦い思い出を回想する物語が静かに語られます。
カズオ・イシグロは後のインタビューで、彼が小説を書き始めたのは内なる日本の記憶を書きとめるためと言っています。5歳まで過ごした長崎の思い出をこの小説のプロットに込めたのでしょう。彼が好きだという小津安二郎の映画に出てきそうな懐かしい昭和の日本がそこにあります。
浮世の画家 (飛田茂雄訳) An Artist of the Floating World (1986)
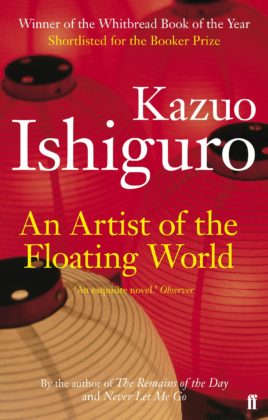
ウィットブレッド賞という、イギリスでの文学賞を取った作品。カズオ・イシグロの2冊めの小説もやはり日本を舞台としています。こちらもやはり彼の「内なる日本の記憶」を書き留める作品であったのでしょう。
前作が子供を無くした母親の哀しみや悔いをテーマにしたのに対し、この小説は若いときに名を馳せた画家、小野があとになって自分の過去を後悔の念を持って回想するというお話です。
戦時中に愛国主義と呼ばれるような作品を発表して成功をおさめたのに、戦争が終わってからはその作品や自分がおこなってきたことが非難の対象になっていることを感じている小野。
彼の回想によってストーリーが展開するのですが、「unreliable narrator」(信頼できない語り手)と呼ばれる手法が使われています。すなはち、小野が述べる過去の記憶は、彼にとって都合の悪い部分をあえて曖昧にしていたり、言い訳のような説明をしているということに読者が気づかざるを得ないところ。
誰にも、思い出したくない過去がある、そのことについて主人公を一方的に非難するのではなく、人間というものはそういうものだと受け止めて静かにそれを描写している作品です。
カズオ・イシグロの作品全体にいえることですが、物語のストーリーの内容そのものよりも、その「語られ方」をも考えながら読むことで、彼の小説の真髄に触れていくことができるでしょう。
日の名残り (土屋政雄訳) The Remains of the Day (1989)
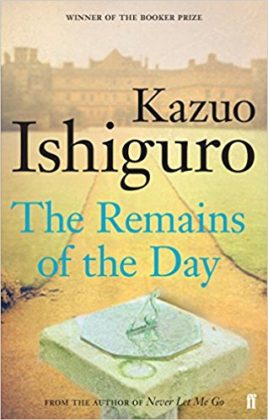
カズオ・イシグロの代表作といってもいい、ブッカー賞受賞作で、彼の作品を読んだことのない人はこの本から読むことをおすすめします。
気鋭の新人作家として注目はされていましたが、まだまだ若く、比較的無名だったカズオ・イシグロ。英国籍をとってはいたものの、日本人の容貌で名前も日本の名前。また、最初の2冊はともに日本を舞台とした小説だったこともあり、「日本の作家」とステレオタイプされることも多かったのです。
「普通の」「ありきたりの」イギリス人作家でなく「日本人の」作家が書く日本を舞台とした作品が目新しいから話題になったり、本が読まれたりすると言われるのに、カズオ・イシグロは何となく、しっくりいかないことを感じていたのではないかと思います。
彼の3冊目の作品は、これ以上ないといえるほど「英国」ふうのプロットです。今どき、普通のイギリス人がバトラー(執事)と呼ばれる人に会ったことがあるでしょうか。
この小説に出て来るベテランの執事スティーブンスはイギリスの古いお屋敷で35年も働いています。彼の父親も「偉大な」執事であり、スティーブンスは自らもそうあるように努力を続けてきました。
主人であるダーリトン卿を偉大な主人だと尊敬し、長い間尽くしてきました。けれども、ダーリントン卿は戦後失墜しその晩年は落ちぶれて悲惨なものでした。スティーブンスはそんなときもダーリントン卿は正しいと信じ続けていたのです。
けれども、新しい主人から休暇を与えられ旅行する中で過去を回想していくうちに彼はダーリントン卿の、そしてみずからの本当の姿に気づき、唖然とするのです。
この作品は恋愛小説でもあり、スティーブンスと女中頭であるミス・ケントンとの淡い関係も描かれています。これについても、スティーブンスという「信頼できない語り手」が読者に伝えるストーリーは自己欺瞞や後悔の念、つまらないプライドと言ったものを感じさせるのです。
といっても、カズオ・イシグロは滑稽なまでに頑なな「羊のような執事」といったスティーブンス、現実に目を背け自己を欺く姿を非難するわけではありません。そんなこともあるのだ、過去のことを思い悩んでも仕方がない、残りの日を大切に生きていくだけだと言っているようです。
英国貴族の執事という、およそ自分とはかけ離れた人物が語る物語ですが、老若男女だれでも多かれ少なかれ自分の人生に関連付けて考える事のできる、名作だと思います。
充たされざるもの (古賀林幸訳) The Unconsoled (1995年)
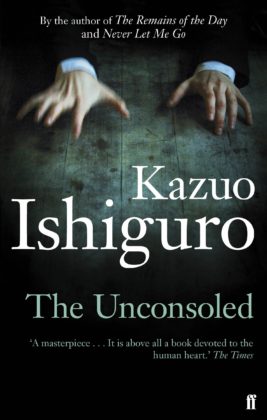
この小説は世界的に有名なピアニスト、ライダーを主人公にした小説で、一人称で語られています。
ヨーロッパの田舎町が舞台となっていて、コンサートのためにそこを訪れるライダーの周りで起こることをライダー自身が語るという手法です。
ライダーの記憶が交錯して、自分が過去に体験した記憶と現在の出来事が複雑にからみあいます。登場人物、過去と現在、その上、地理的な空間も錯綜した世界で、読者はまるで夢の中を歩いているような気になるでしょう。
カズオ・イシグロは記憶のテクスチャーに魅了されているようです。語り手の記憶から引き出されるものは、さまざまな感情が入り乱れ、不鮮明で読む人によって印象も変わってくるでしょう。
カズオ・イシグロ ワールドを堪能するにはうってつけの小説ですが、彼の著作の中ではイギリスでも賛否両論に分かれる作品です。かなり長編で普通の小説にあるようなわかりやすいストーリー展開ではないので、初めて彼の作品を読む人にはおすすめしません。
わたしたちが孤児だったころ (入江真佐子訳) When We Were Orphans (2000)
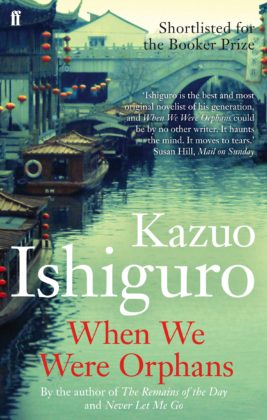
この小説も「信頼できない語り手」であるイギリス人探偵、バンクスの一人称で物語が展開します。
戦時中の上海を舞台に、バンクスが行方不明になった両親を探しに行くストーリーに、彼の過去の記憶が織り交ぜられて語られていきます。
バンクスが子供だったときの上海をはじめ、ディテールが詳細に書かれていて、読者は物語の世界にすぐ引き込まれます。
はじめは、探偵小説かと思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。読み進んでいくうちにカズオ・イシグロのテーマである人間の記憶、そしてそれが信頼できない主人公によって語られるとどうなるのかという展開がわかるでしょう。
バンクスが上海で出会うのは両親を窮地に陥れた敵や愛する女性、子供の頃の幼馴染みである日本人ばかりではありません。自身の記憶にある「私たちはみんな孤児だったんだ」という思い、永遠に探すことのできないものをそれと知りながら探し続けなくてはならない切なさです。
わたしを離さないで (土屋政雄訳) Never Let Me Go (2005)
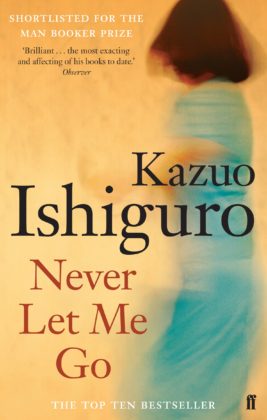
これまでプロットや登場人物はさまざまではあるが、実際にありそうな物事を書いてきたカズオ・イシグロが初めて「クローン人間」という架空の世界を描いた作品です。
それだけを聞くとSFなのかと思いがちですが、彼は「クローン人間」をテーマにしたかったわけではなく、長く生きられない人間集団の「生」に関する思いを書きたかったのだと言っています。
カズオ・イシグロの真髄が発揮されている小説で、この作品も彼の本に馴染みがない人におすすめのものです。
作品の主要人物はキャシー、トミー、ルースの3人の若者です。キャシーが過去を回想する形でストーリーが展開されますが、はじめは1990年代末のイギリスの寄宿学校が舞台であり、読者はすべてを知らされていません。キャシーが過去の思い出を書いていくうちに、徐々に彼らがどのような「人間」であるのかが読者に明らかになっていくという展開なので、次が知りたくなってどんどん読み進めていけるでしょう。
およそ現実世界とはかけ離れたテーマを扱っているようにみせながら、実は私達の誰もが直視しなければならない人生のリアルがそこにあります。いつか終わりが来るという事実、自分では変えることのできない運命、その中ですべてを受け入れて、大切な人たちとともに残りの時間を生きていく切なさを伴う、静かな幸せ。
読み終わったあとに、「毎日をたいせつに生きて行こう、自分にとって大事に思う人達にもっと思いやりを持って。」と思わせてくれる、というとなんか嘘っぽい感じですが、素直に心静かにそう思える読後感があります。
夜想曲集 (土屋政雄訳) Nocturnes (2009)
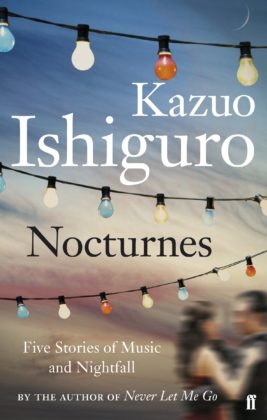
カズオ・イシグロ初の短編集で、書き下ろし連作5編が収録されています。
「音楽と夕暮れをめぐる5つの物語」というテーマで、さまざまな人物が様々な場所で音楽と出会い、人と出会い、過去を回想し、人生に思いを馳せるストーリー。
ひとつずつが独立した物語でありつつ、根底に流れる同一のテーマから編まれた短編集はさながら音楽アルバムのようです。
それぞれの物語の背景は時代も場所も異なり、それに合わせてさまざまなジャンルの音楽が各作品を彩っており、かつてミュージシャンを目指していたカズオ・イシグロの音楽への造形も感じさせる短編集です。
両親も音楽が趣味で、彼は出勤前にピアノを弾くお父さんのピアノの音に起こされていたと言っていて、自らも幼い頃からピアノをたしなんでいました。若い頃はギターを弾き、ボブ・ディランのような歌を作曲して歌っていたといいます。
この短編集には、彼の全作品に通じる「記憶」のテーマがあり、コメディ的な作風のものがあったり、彼自身も他の長編小説に比べ、比較的気軽に楽しんで書いたのではないかと思うところがあります。
彼の長編小説がワーグナーのオーケストラなら、こちらは様々な小曲を集めた音楽アルバムといったところでしょうか。
最初は短い作品から試してみたい人におすすめの本です。
忘れられた巨人 (土屋政雄訳) The Buried Giant (2015)
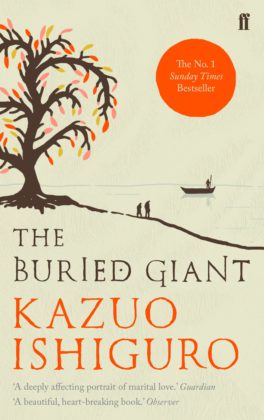
この作品は舞台が古代イングランドとなっていて、鬼やドラゴンが登場するというので、一見ファンタジー小説?と思わせるのですが、実は違うんですね。
カズオ・イシグロはファンに同じようなプロットを読ませないぞ、驚かせてやるぞといつも考えては新しい作品を考えるのかなと思います。
これまで彼はおもに個人の記憶について様々な角度から作品を書いてきました。この作品は、個人の記憶というよりは、ある社会、コミュニティー、または家族が共通して持っている記憶について書かれています。そして、それは覚えておきたい輝かしい記憶ではなく、忘れたい負の記憶といってもいいものです。
生き残るために、前に進むために、忘れなければいけなかった記憶と言うものは誰にもあるでしょう。そして、ある共同体(国であったり、夫婦であったり、民族であったり)が共有する記憶にも地中深くに埋めておきたい巨人のようなものがあるんですね。
カズオ・イシグロは、国家という名でおこなわれた政治的な所業、例えば第2次世界対戦のときに各国が行った残虐な行為などのことを書きたかったのかもしれません。でも、あえてそれを古代イングランドという架空の世界に置き換えて伝えようとしています。
日本でも他の国でも、戦争から帰って来た兵士たちが戦中のことに口を閉ざして語りたがらなかったこと、一般国民の中にも戦時中は愛国心に燃え戦争賛美していた事実がなかったかのように戦後の復興にはげんだことなどが連想されます。
それらの記憶は、直視するのがつらいし、自分や自分が大切だと思う人や共同体を否定することにつながるので忘れたいと思っている、そういう共通の認識が共同体ぜんたいであるのでみんなで「巨人」を埋めてしまおうとする、でもそれは本当に忘れていいものなのか。
前に進むために過去の負の記憶を忘れることは正しいのか、それしか方法がなかったのか、そして私たちは本当にそういう過去を忘れ去ることはできるのか。つらい過去でも忘れずそれについて考え反省することが未来のために大切なことではないのか。
考え始めると実に深淵なテーマををファンタジー風の物語になぞらえて、彼特有の静かな語り口で感情的になることなく綴っている作品です。
カズオ・イシグロについての関連記事
カズオ・イシグロ インタビュー「小説家になったのは内なる日本の記憶を書きとめるため」


ネタバレを書かないでくれますか?続きを読む気が失せた。